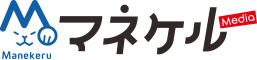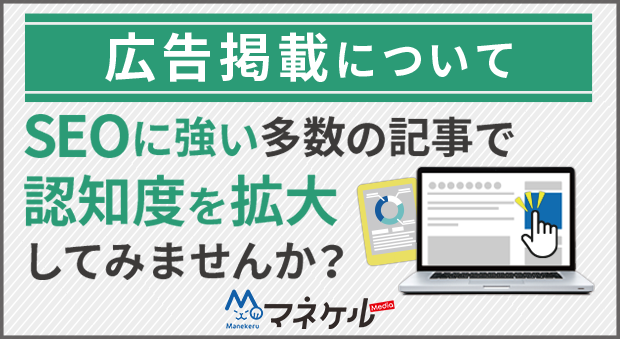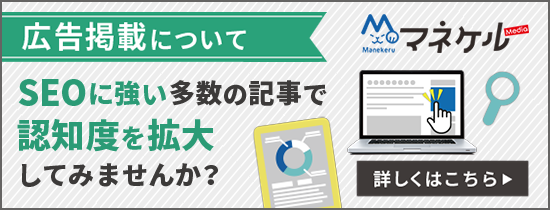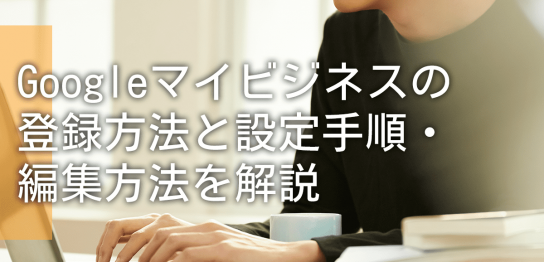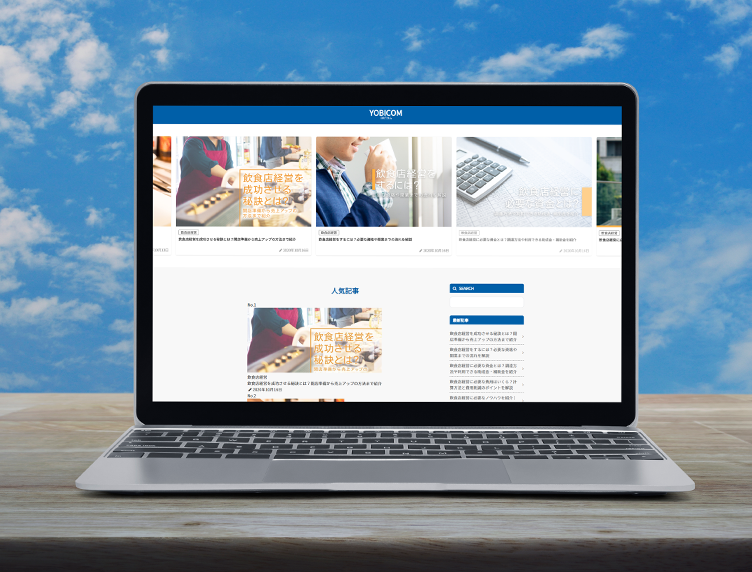多店舗展開とは、店舗数を増やすことで売上拡大や認知度アップなどを図る戦略です。人材管理や品質の標準化といった課題がある一方で、成功することでスタッフの技術向上やサービス品質向上も期待できます。多店舗展開とはどのような特徴があり、競争力を高めて競合に勝つためにはどのようなことに留意して出店戦略を展開すればよいのでしょうか。今回は、多店舗展開のメリット・デメリットや出店タイミングなどについて解説していきます。
目次
多店舗展開とは?業種や展開方式を解説

企業が複数の店舗を展開し、店舗数を増やすことで売上拡大を図る戦略である多店舗展開には、主に「直営店方式」と「フランチャイズ方式」の2種類の方法があります。それぞれの特徴や、どのような業種が適しているのかを解説します。
多店舗展開に適した業種
多店舗展開を図るのに適した業種は、主に下記のようなものがあげられます。
・飲食サービス業…レストランや食堂、専門料理店、カフェなど
・生活関連サービス業…サロンやジム、マッサージ店、クリーニング屋など
・小売業…コンビニエンスストア、ガソリンスタンド、アパレルショップや雑貨屋、パン屋など
・教育・保育業…学習塾やカルチャースクール、幼稚園、保育園など
・金融・保険業…銀行や保険代理店など
・医療・福祉業…クリニックや介護施設、整体など
・駐車場業…コインパーキング
もちろんこれらに限ったものではないので、各業種の特徴や市場規模を調査する必要があります。
飲食店の複数店舗経営について詳しくは、下記の記事もあわせてご覧ください。
直営店展開の特徴
直営店展開とは、自社で運営する店舗を増やす方法を指します。出店による設備投資や運用管理、スタッフの採用などの業務はすべて自社で行います。店長・マネージャーとなるスタッフは自社社員が担当することが多く、スタッフ教育や運営管理も自社からの指示を元に進められるため、比較的容易に運営することが可能です。
店舗の売上はすべて自社の利益となるため、売上が大きいほど利益も大きくなりますが、店舗を賃貸する場合や人件費といった費用も賄わなくてはならないため、売上が小さい場合は赤字も考えられます。
フランチャイズ展開の特徴
フランチャイズでの多店舗展開とは、加盟店となる他の事業者に自社のブランドを提供して運営してもらう方法を指します。加盟店へ自社の開発メニューやノウハウを提供する代わりに、加盟金や売上手数料といったロイヤルティ(使用料)を受け取るというビジネスモデルです。
直営店展開と異なることとして、自社とは関係のない人が店長や経営者となるため、自社としてのスタッフ教育や運営が充分伝わらないことがあげられます。一方で、経費のほとんどはフランチャイズとなるオーナーが負担するので企業側としては利益率は高いといえます。また、フランチャイズ店での評判が自社のイメージに影響することも注意しておきましょう。
フランチャイズについて詳しくは、下記の記事もあわせてご覧ください。
多店舗展開で得られる5つのメリット
- 売上アップにつながる
- 認知度アップが期待できる
- リスク分散ができる
- 仕入れコストを削減できる
- スタッフのモチベーション向上につながる
複数の店舗を展開する多店舗展開では、さまざまなメリットを得ることが可能です。ここでは、多店舗展開で得られる5つのメリットを解説します。
売上アップにつながる
複数の店舗を展開して商圏を拡大することで、それに比例して全体としての来客数が増加し、売上アップを期待することができます。新たな出店場所での新規顧客を獲得できるのは多店舗展開ならではのメリットといえるでしょう。初来店の顧客がリピーターとなることで、他店舗の利用も期待でき、多店舗展開というブランド価値によって新たな収益増加も見込めます。
認知度アップが期待できる
店舗数が増えることで露出が増え、認知されやすくなることが見込めます。さらに認知度が向上することで人気のある企業だというブランディングや、宣伝費用をかけなくても集客につながるなどの販促力向上も期待できるでしょう。また、特定の地域に集中して多店舗出店することでその地域のシェアを獲得する「ドミナント戦略」も多店舗展開だからできる強みともいえます。
ドミナント戦略について詳しくは、下記の記事もあわせてご覧ください。
リスク分散ができる
店舗経営とは、立地や競合他社などの市場の影響を受けやすく、少数での店舗展開の場合、ひとつの店舗が赤字となるだけで経営全体に影響を受けます。しかし多店舗展開の場合は、店舗同士で収益を補いあうことで他店舗の赤字をカバーすることができ、経営リスク分散、安定した店舗経営が可能となります。
仕入れコストを削減できる
多店舗展開の場合、仕入れを一括で行う大量購入により、仕入れ単価を減少させ、利益率の向上を見込めます。さらに本店でまとめて仕入れを行ったり、支店での発注を他店に分散させたりするなど、仕入れ業務の効率化も図れるだけでなく、大量購入による仕入れ先への影響力により、仕入れ先に対しての商品の協力も期待できます。
スタッフのモチベーション向上につながる
店舗数が増えることで、店長、マネージャー、リーダーなどのポジションも増えていきます。さらに地域を越える店舗数になることでエリアマネージャーというポジションも必要となります。スタッフにとって昇格・昇給のチャンスが増えることでモチベーション向上につながり、スタッフの技術向上、サービス品質の向上も期待できるでしょう。スタッフを増員させることは、店舗間でのサポート体制の充実にもつながり、スタッフが休暇を取りやすくなり、スタッフの満足度やパフォーマンスの向上にもつながっていきます。
多店舗展開で気をつけるべき4つのデメリット
- 経費が増加する
- 人材の管理と育成が難しい
- 品質が標準化しづらい
- 経営管理が複雑になる
店舗数を増やすことで売上拡大を期待できる多店舗展開ではありますが、デメリットも存在します。どのような点に気をつける必要があるのか、4つの点について解説します。
経費が増加する
多店舗展開として新店舗をオープンさせるとなると、当然新店舗の初期費用が必要となります。また、出店地域や店舗の規模に応じては高額になることも考えられ、売上でそれらの必要経費を賄えない場合には赤字になる恐れもあります。多店舗展開は仕入れコスト削減につながるものの、新店舗の物件取得費、人件費、水道光熱費といった経費の負担をいかに効率化して減らすかがポイントでしょう。そのため、新店舗出店の際は計画的な資金調達を想定し、さらにどのような支援制度を利用できるかということも調べておくとよいでしょう。
人材の管理と育成が難しい
多店舗展開の場合の課題のひとつとしてあげられるのは、人材確保と人材管理です。複数の店舗になることで、スタッフ同士のコミュニケーションを図ることが難しくなり、管理側も店舗ごとに細かなサポートを行うことができなくなることも考えられます。フランチャイズ展開の場合は特に、自社とは関係のない人が店長や経営者となるため、自社としてのスタッフ教育が難しくなります。そのため、採用は自社が行い、管理についてもマニュアル化するなどの対策も必要でしょう。
品質が標準化しづらい
人材管理やスタッフ教育と同様に、多店舗展開では商品・サービスの均一化、品質の標準化も課題となります。たとえば飲食店の場合は、提供する食事やサービスがスタッフのスキルに依存してしまったり、属人化してしまったりして店舗やスタッフによってばらつきが生じる恐れもあります。商品・サービスの均一化を図るには、店舗管理マニュアルや業務・接客マニュアルを作成するのがおすすめです。ただし、マニュアル作成にも時間と手間がかかることも念頭におきましょう。
経営管理が複雑になる
多店舗展開になると、店舗によって顧客の数も商品の種類も異なるため、結果的に仕入れの数も変わります。さらに店舗によってスタッフの数も違うため、一店舗での経営よりも経営管理が複雑になると考えられます。一元管理できるための組織づくりやシステムの導入も必要となるでしょう。
多店舗展開を成功につなげる4つのポイント

一店舗よりも複雑な多店舗展開の運営は、メリットもありつつ、難しい点も多くあることがわかりました。そのうえで多店舗展開を成功させるにはどのようにしたらよいか、4つのポイントを解説します。
綿密な資金繰りを行う
多店舗展開を図るとなると、当然資金も必要となります。資金を調達する際に融資を検討するのであれば、国が出資する日本政策金融公庫や銀行融資、国の補助金や助成金など、どの手段が自社に必要な資金を集めやすいかを検討してみましょう。手段によっては創業計画書や借入申込書、見積書や通帳などの必要とする書類が異なるため、条件や方法を確認しながら、経営を圧迫しないような融資の返済方法など、綿密に資金繰りを検討していきましょう。
マニュアルを作成し、業務を標準化する
多店舗展開のデメリットの項目でも解説しましたが、多店舗展開では商品・サービスの均一化、品質の標準化が課題となります。商品・サービスをどの店舗でも均一に提供できるように、業務マニュアルを作成して、どの店舗のどのスタッフでも均一にサービスを提供できる環境を整えましょう。業務向けのシステムがあれば、自動化することで均一なサービス提供もできます。
撤退ラインを設定しておく
新店舗が赤字になってしまうと、他店舗や会社全体の経営の悪化にもつながることが考えられます。たとえば「赤字が12か月連続で生じた場合」などのように、投資金額などから算出した撤退条件を事前に明確にしておく必要があります。
多店舗展開で意識したい戦略

綿密な資金繰りや業務の標準化など、多店舗展開の成功に向けたポイントのほかに、どのようなことを意識すればよいのでしょうか。最後に多店舗展開を計画する際に意識しておきたい戦略について3つ解説します。
出店戦略を立てる
多店舗展開に限らず、新規出店の場合に特に重要なのは立地です。1店舗めが成功したからといって、2店舗め以降も同様に成功するとは限りません。ターゲットとする地域の需要や顧客のニーズ、競合状況などの市場調査を入念に行いましょう。また、出店のタイミングは1店舗めが安定的に黒字化しているかがポイントです。1店舗めの利益が充分であれば、2店舗めの運転資金をカバーできます。反対に、2店舗めが失敗してしまうと、1店舗めにも影響してしまうので、1店舗めの業績次第では出店を見送る必要もあります。
出店戦略についてくわしくは、下記の記事もあわせてお読みください。
自店舗が優位となる戦略を立てる
立地の市場調査に続いて重要なのは、競合の分析です。競合他社の特徴、強みや弱点、市場におけるポジションなどを徹底的に分析し、そのうえで、自店舗が差別化できるポイントや優位となるポイントを見つけ、自店舗が優位となれる戦略を立てましょう。差別化できるポイントには価格や商品・サービスの充実性などがあげられます。また、顧客ニーズや市場の変化に対応できるように柔軟な戦略の調整や定期的な改善を図りましょう。
ブランドイメージやコンセプトを統一する
多店舗展開では、特にフランチャイズ展開の項目で説明したような自社としてのスタッフ教育や運営が充分伝わらないことがある点や、商品・サービスの均一化や品質の標準化も課題となります。そのため、どの店舗でも一貫したブランドイメージやコンセプトを展開できるように、スタッフ教育の徹底や適切な人材の確保により、店舗としてのブランドの価値観やビジョンを全体で共有することが重要です。
まとめ

今回は、多店舗展開についてのメリット・デメリットや、出店のタイミング、意識したい戦略などを解説しました。商品・サービスの均一化や業務の統一化を図るのが課題となる多店舗展開ですが、市場調査や競合分析を徹底することで、売上や認知度向上につながるというメリットがあります。出店タイミングや戦略を綿密に立てながら、多店舗展開の成功に向けて踏み出してみてはいかがでしょうか。