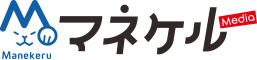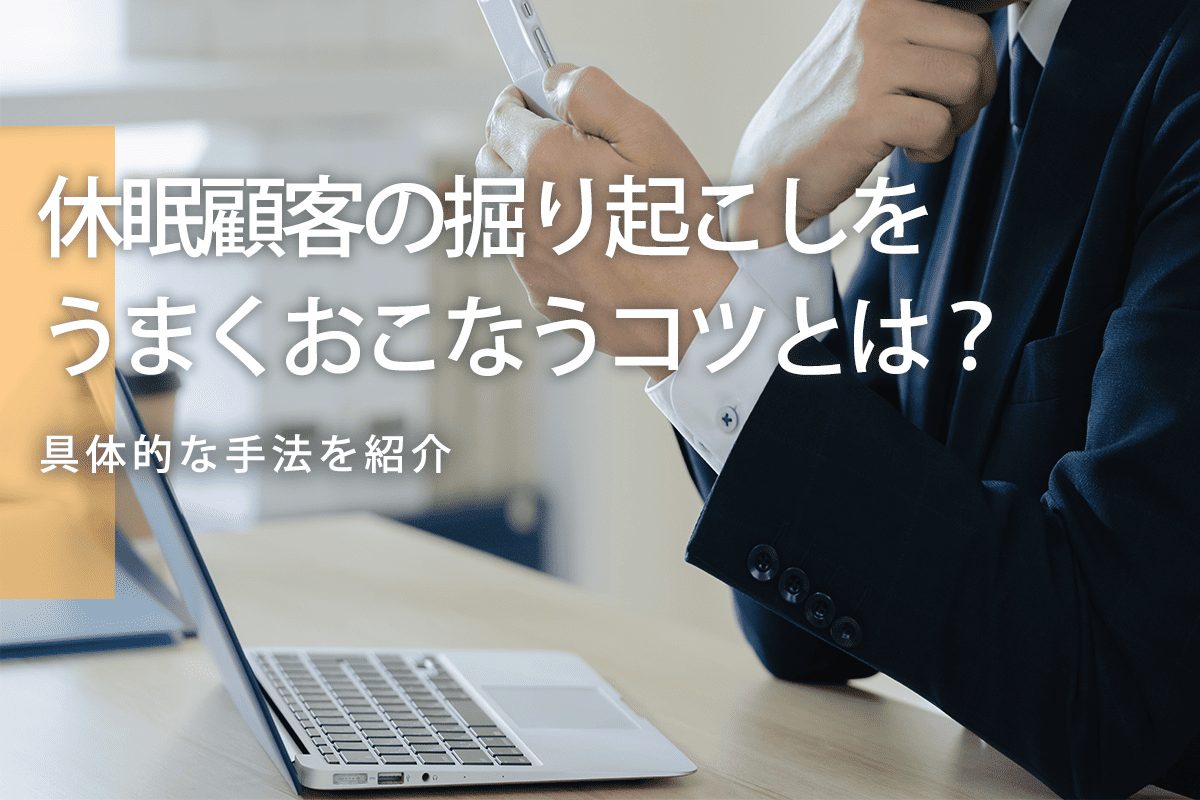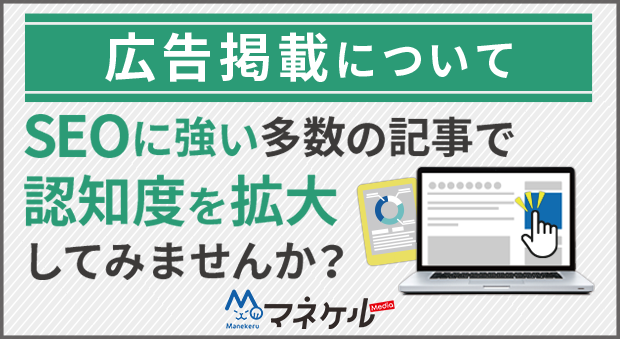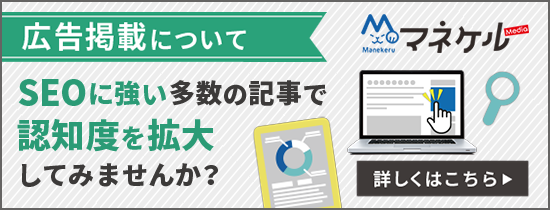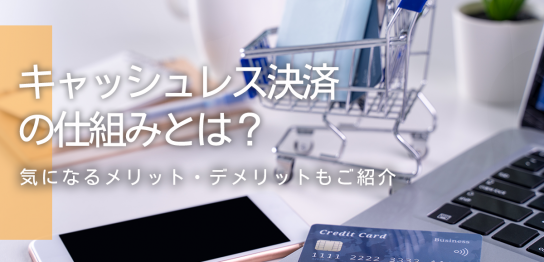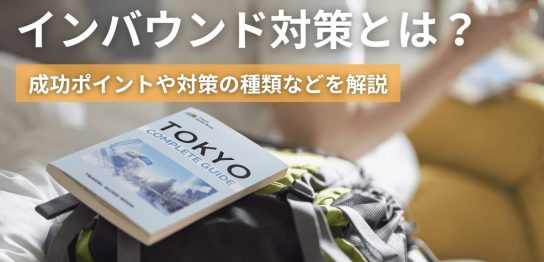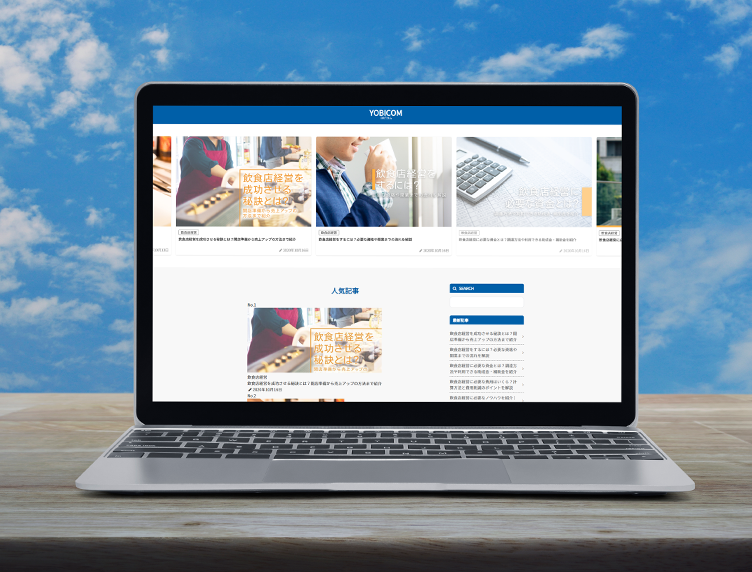企業の売上を高めるためには、新規顧客の開拓や既存顧客のつなぎ止めだけでなく、「休眠顧客」の掘り起こしも大切です。ただし、休眠顧客になる原因やアプローチ方法はさまざまで、企業や商品・サービスによっても異なります。
今回は、休眠顧客の定義や原因など基礎的な概要から、掘り起こしを行う重要性、実際のアプローチ方法などについて詳しく紹介します。
目次
休眠顧客とは?

休眠顧客とは、「過去に購買やお問い合わせなどを行った履歴はあるものの、それ以降一定の期間商品やサービスを購入していない顧客」のことを指します。すでに1度は利用していることから、商品やサービス、企業やブランドについてある程度の知識があり、再度利用する見込みのある顧客となります。よって、「放置された状態の見込み顧客」ともいえるでしょう。
休眠顧客の具体的な特徴
休眠顧客の具体的な例には以下のようなケースがあります。
- 1回限りの商品の購入やサービスの利用で終わってしまっている顧客
- 過去複数回にわたって取引があったが、直近では取引が無くなった顧客
- 問い合わせや資料請求をしたまま、その後アクションを起こしていない顧客
- イベントへの参加などで興味を示してくれたが、それ以降動きがない顧客
このように休眠顧客とされる基準は期間やアクションなどによってさまざまです。一般的に多いのは、最終購入日から半年〜1年半程度の設定です。また、BtoBの場合、購入や利用など取引履歴がない場合でも、見積もりや商談など過去に何らかのやり取りがあれば休眠顧客とするケースもあります。
なお、同様の言葉として「離反顧客」が挙げられますが、離反顧客は「他社に流れてしまった顧客」のことをいいます。自社の商品やサービスよりも他社のものに魅力を感じてしまっているので、休眠顧客以上に取り戻すのが難しいといわれています。
休眠顧客をうまく掘り起こすためには、アプローチする顧客が休眠顧客なのか離反顧客なのかを明確にしておくことも大切です。
休眠顧客が生まれる原因
休眠顧客が利用をやめてしまった原因次第では、アプローチしても掘り起こしが難しい場合もあります。顧客によって状況は異なるため、何が原因で休眠顧客になってしまったのかをなるべく正確に把握しておくことが大切です。休眠顧客になってしまう原因には主に以下のような例があります。
- 商品やサービスに不満を持った
- 商品やサービスを購入する必要性がなくなった
- 過去に利用や購入をした経験や商品の存在自体を忘れてしまった
このように、自社の商品やサービスに原因があるケースだけでなく、顧客の生活や環境の変化、時間などによる影響もあります。提供している商品やサービス、業界などによってどのようなケースに当てはまるかは変わるので、自社の場合はどうなのかを考えてみましょう。
休眠顧客を掘り起こすことの重要性

集客において新規顧客を獲得することは大切ですが、まだ自社のことを知らない相手や興味を持っていない相手にアプローチするには、多くのコストや手間がかかる可能性があります。また、情勢や社会的な変化に左右されたり、競合他社が増えて競争が激化したりなど、周囲からの影響によって新しい顧客の呼び込みが難しくなるケースもあります。
一方で、すでに何らかの取引をした経験がある休眠顧客は、新規顧客よりも利用や制約につながる可能性が高いことが期待できます。顧客の情報もすでに持っているため、確度の高い顧客層のみに絞ったアプローチを行うことができ、コストや手間を抑えることにつながります。「1:5の法則」ともいわれるように、新規顧客の獲得には、既存顧客を維持するための5倍のコストがかかるとされているため、休眠顧客を掘り起こして既存顧客として維持することが重要になります。
ただし、集客では状況に応じて、既存顧客と新規顧客のどちらに対しても注力する必要があります。以下の記事では、新規顧客を獲得する方法を紹介しているので、あわせて確認してみてください。
休眠顧客の掘り起こしに適した方法とは?
では、具体的には休眠顧客の掘り起こしはどうすればできるのでしょうか。
代表的な方法として、次の5つが挙げられます。
- ステップメールなどのメール配信を行う
- DMを送付する
- 電話営業をする
- 手紙を送る
- MAツールを活用する
それぞれの特徴を理解しておけば、企業が実践すべきアプローチを考えやすくなるでしょう。以下では、それぞれの方法について詳しく説明します。
ステップメールなどのメール配信を行う
休眠顧客へのアプローチとして一般的によく活用されているのがメール配信です。顧客にあわせて内容を変えたメールやステップメールなどを送ることで、顧客に適切なタイミングでの接触を図れます。
ステップメールとは、企業の商品やサービスを購入した経験がある顧客に対して、あらかじめ用意しておいたメールをスケジュールに沿って配信する方法です。
これはメールマーケティング手法のひとつで、購入以外にも、無料会員登録やカスタマーセンターへの問い合わせなど、さまざまなアクションに応じてメールの内容や送信時期を設定できるのが特徴です。
休眠顧客の掘り起こしにステップメールを活用する際は、「この企業の商品やサービスをもう一度購入してみたい」と感じてもらえる内容にしなければなりません。たとえば、メールにクーポンを添付したり、期間限定キャンペーンを案内したりすることが挙げられます。メールの内容が休眠顧客にメリットを感じてもらえるものであるほど、掘り起こしに成功しやすくなります。
ステップメールのつくり方やコツは以下の記事で詳しく紹介しています。
DMを送付する
DM(ダイレクトメール)は、特定の個人に向けて広告やパンフレット、はがきなどの案内を郵送する方法です。メールを開かなければ見てもらえないステップメールとは違って実際に手元に届けるため、より顧客に接触しやすい媒体といえます。
形に残るという点も特徴で、保管してもらうことができれば何度も見てもらえる機会が生まれます。また、大衆向けにアピールするチラシやテレビといった手法よりも個別性を出しやすいため、特別感を感じてもらえるというメリットもあります。
しかし、DMはメールよりも作成や送付の手間と費用がかかりやすいのがデメリットです。資材の印刷や投函の手間などがかかるうえに、顧客に直接届けられるといっても、すぐに捨てられたり、そもそも開封してもらえなかったりするケースもあります。よって、興味を持ってもらえるようなデザインや文言、見せ方を考えることが大切です。クーポンや来場特典などを設けておくと、休眠顧客を掘り起こしやすくなるでしょう。
DMについても、以下の記事で効果やメリットとデメリットなどについて詳しく解説しています。
電話営業をする
インサイドセールスやコールセンターを活用して、休眠顧客に直接電話をかけるのもアプローチ方法のひとつです。
文章では伝わりにくい内容でも、口頭で説明することにより魅力を感じてもらいやすくなるので、扱う商品やサービスによっては、電話が適している可能性があります。また、会話を通じて休眠顧客になった原因を把握できれば、顧客のダイレクトな意見を今後の事業運営に活かすこともできます。
ただし、頻繁に電話をかけすぎると、かえって迷惑に感じられる可能性が高まるので注意が必要です。「期間限定セールの案内」や「新商品体験会の案内」など、顧客にメリットを感じられる内容であるほど、掘り起こしを成功させやすくなるでしょう。
なお、電話営業を行う際は事前に「トークスクリプト」と呼ばれる台本を用意するのがおすすめです。事前に話の内容や想定される顧客からの質問をまとめることで、スムーズなやり取りにつながります。以下の記事では、トークスクリプトのつくり方やポイントを紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
手紙を送る
直筆の手紙を送れば、メールよりも休眠顧客に読んでもらいやすくなると言われています。また、内容によっては顧客によい印象を与えられるので、商品やサービスの購入につなげやすくなるでしょう。
しかし、直筆の手紙は作成できる数に限りがあるのがデメリットです。メールやDMのように、一度に多くの休眠顧客へ送付できるわけではないので、ある程度ターゲット顧客を絞り込む必要があります。
MAツールを活用する
マーケティングのさまざまな業務を自動化するシステムやツールのことを「MA(マーケティング・オートメーション)」と呼びます。顧客情報の管理や利用状況に基づいたセグメント分け、行動データの分析、顧客個人にあわせてパーソナライズしたメール配信やABテストなど、さまざま業務に活用することができます。
ただし、MAといってもシステムやツールによって機能は異なるため、何を自動化してどう活用したいのかなど、事前によく検討したうえで導入することが大切です。
また、関連する言葉に「CRM(Customer Relationship Management)」もあります。こちらは「顧客関係管理」とも呼ばれる通り、顧客との関係性を良好にする取り組みを意味します。
CRMを行うためのツールやシステムも多数提供されており、顧客の情報や行動パターンの管理から、顧客に合わせた対応の提案を行ってくれるものまでさまざまです。MAツールとあわせて、必要な機能を持ったものがあるか探してみるとよいでしょう。
休眠顧客の掘り起こしをうまくおこなうコツとは?
ここまでは、休眠顧客を掘り起こしする際の具体的な方法について説明しました。これらの方法によって得られる成果を高めるためには、次の3つのコツを意識しておくことが大切です。
- 休眠顧客をなるべく早く発見する
- ターゲットにする休眠顧客を明確にする
- 掘り起こしに使う具体的なアプローチ方法を考える
以下では、休眠顧客の掘り起こしをうまくおこなうコツについて、詳しく説明します。
休眠顧客をなるべく早く発見する
休眠期間が長くなるほど、顧客はサービスや製品に対する感情がなくなっていくため、休眠顧客の掘り起こしが難しくなります。そのため、「休眠顧客化している」と認識した時点で、何らかのアプローチをするのが理想です。
そのためには、まず自社製品における休眠顧客の期間設定を明確にしておきましょう。自社の商材が一般的にどのようなサイクルで利用されるものなのか、顧客はどういう利用の仕方をしているのかなどを基準に、具体的に「いつから休眠と捉えるべきか」を定めます。そして、それらの期間に該当した顧客がすぐにわかるような仕組みを整えましょう。
顧客が多い企業であれば、先ほど紹介したMAツールやCRMツールを活用して休眠顧客の存在を自動的に通知してくれる仕組みを整えておくのもよいでしょう。
ターゲットにする休眠顧客を明確にする
休眠顧客がいることを発見したら、次にターゲットを明確にしておく必要があります。
一言で「休眠顧客」といっても、さまざまな属性の顧客がいるため、休眠顧客全員に同一のアプローチをしても、結果的に得られる成果が限定的になってしまうからです。
実際にターゲットとする休眠顧客を絞り込む手法として、「新製品をよく購入していた人」や「価格帯の安い商品を購入していた人」、「高額商品の購入履歴がある人」のように、過去の購入履歴から決める方法が挙げられます。
また、年代や性別、居住エリアといった属性から決めるのもよいでしょう。ターゲットごとに適切なアプローチができれば、企業の商品やサービスをもう一度手にとってもらいやすくなります。
掘り起こしに使う具体的なアプローチ方法を考える
休眠顧客を発見し、ターゲットに設定ができたら、アプローチする方法を具体的に考えていきます。先述した具体的な掘り起こし方法などの中から、ターゲットに応じて慎重に決めることが大切です。
また、実際に掘り起こし方法を決めるときは、ターゲットを設定した理由やその方法を選んだ理由をはっきりさせておきましょう。具体的には、「30代向けの化粧品を販売したいから、20代で自社製品の新商品をよく購入していた人に対して、商品説明会の案内をデザイン性のあるDMでアピールする」といったことが挙げられます。
論理的に戦略が練られているほど、掘り起こしが成功したかどうかを評価しやすくなるので、さらに精度の高い施策につなげられるでしょう。
まとめ

ここでは、休眠顧客の定義や掘り起こしが期待できる具体的な手法、うまく休眠顧客を掘り起こすためのコツなどについて説明しました。
業種や提供する商品・サービス、休眠顧客の属性によって適したアプローチが異なるので、さまざまな手法を試しながら効果を検証していくことが大切です。ここで説明した内容を参考にして、うまく休眠顧客を掘り起こせるようにしておきましょう。
記事のURLとタイトルをコピーする