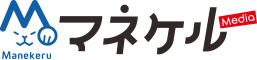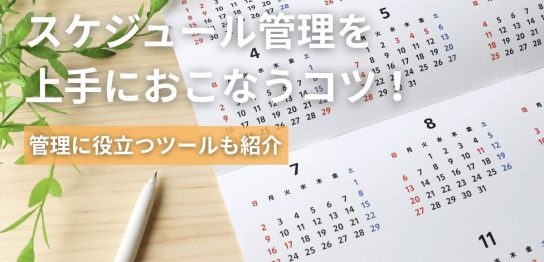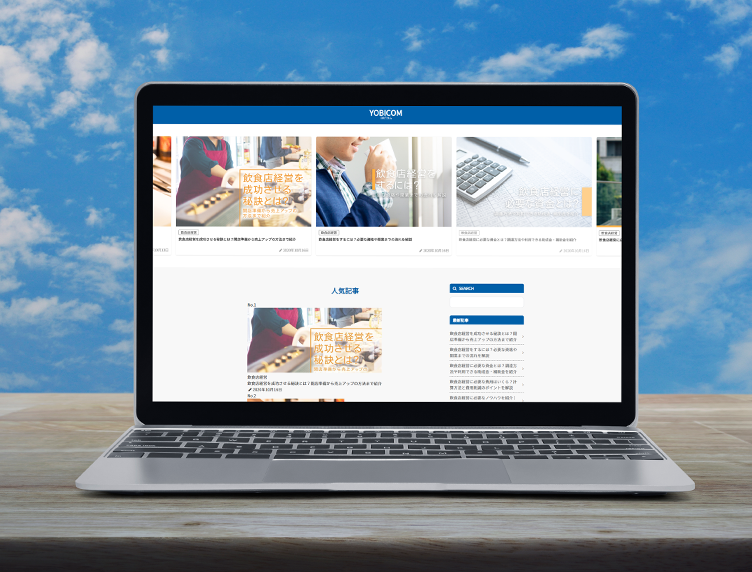ひとつの商圏に大型店舗やスーパーマーケット、コンビニエンスストアなど、小売店舗がその商圏の需要を超えて出店している状況を「オーバーストア」と呼びます。オーバーストアの競争に負けた店舗は、撤退や廃業を余儀なくされます。そもそも、なぜオーバーストアは発生するのでしょうか。今回は、オーバーストアについて発生する原因と、オーバーストアがもたらす影響、その対策について解説していきます。
目次
オーバーストアとは

オーバーストアとは、小売店舗などの商業施設が、ある商圏の需要以上に出店している状況を指す和製英語です。大型ショッピングセンターなど大手企業の地方都市への出店や、コンビニエンスストアなどでの特定の地域に集中的に出店することでシェアを獲得するというドミナント戦略も要因のひとつとされています。
オーバーストアにより、ひとつの市場での利益が分散されてしまい、個々の店舗の業績の低下や、もともと存在する地元小売店の経営への影響が問題となっており、さらに大型店撤退により空き家となった建物の廃墟化も課題となっています。
オーバーストアの主な発生原因
ある商圏における需要以上に商業施設が出店するオーバーストアの発生にはいくつかの要因があります。ここでは、オーバーストアの主な発生原因について3つ解説していきます。
- 積極的な出店や拡大戦略
- 市場・景気・消費行動の変化
- 少子高齢化の進行
積極的な出店や拡大戦略
商業施設が積極的に出店する理由は、それぞれの企業の拡大戦略が目的です。そのため、大手企業は地方へも急速な商業施設開発をすすめ、さらにチェーンストアなどの小売企業が集中的に出店を重ねることで、結果的な供給過剰、オーバーストアにつながっていきます。
大型店の出店を規制して、中小の小売業を保護することを目的に1974年には大規模小売店舗法が制定されましたが、大手小売資本や海外からの圧力もあり、廃止されました。オーバーストアには歯止めがかけられないのが現状となっています。
市場・景気・消費行動の変化
オーバーストアには、時代の流れや消費者行動の変化による市場変化、競争環境の変化も一因となっています。典型的な例では、1990年代のバブル崩壊があげられます。バブル経済期に膨らみ続けた消費者の購買意欲を当てにした出店ラッシュが、バブル崩壊によって消費の落ち込みが長期化し、オーバーストア化が進んだ結果、店舗数が減少しました。
さらに近年ではオンラインショッピングや電子書籍の一般化により、書店の廃業が増えたというのも一例としてあげられます。景気後退による消費の落ち込みと、オンラインショッピングなどの消費者行動の変化が、オーバーストアの要因のひとつとなっています。
少子高齢化の進行
少子高齢化、人口減少も、地域の購買力の低下や需要の縮小につながり、オーバーストアが生じる一因となります。高齢者ニーズへの再対応や、過剰出店の是正も求められます。
オーバーストアがもたらす悪影響

オーバーストア化が進むと店舗や地域にとってさまざまなマイナス効果が生じます。ここでは、オーバーストアがもたらす悪影響について3つ解説していきます。
売上の減少
同じ地域において店舗過剰となるオーバーストア化が進むことで、ひとつの市場での消費者需要が分散されてしまい、個々の店舗の売上の減少や業績の低下につながります。なかでも小売店舗の売上高は、近年減少傾向にあるといわれています。
価格競争の激化
オーバーストア化により価格競争が激化すると、割引によって坪あたりの売上高が減少し、利益率の低下が生じます。大型店舗では人員削減によって販売効率を高めるなどの対応も可能ですが、個人商店など小規模店舗では人員削減は難しく、運営コストを賄えなくなる長期的な経営リスクが高まる恐れもあります。
小売店の撤退・廃業
売上の減少や価格競争の激化によって体力を保てなくなった小売店は、最終的には撤退・廃業を選択せざるを得なくなります。なかにはオーバーストア化によって自社製品・サービス同士が売上を奪いあう「カニバリゼーション」が生じ、売上減少につながっている場合もあります。
小規模店舗の撤退・廃業により、市の中心にあった商店街がシャッター通りとなり、郊外のショッピングセンターだけが勝ち残ることで大商圏の郊外化につながります。一方で、郊外のショッピングセンター同士でもオーバーストアが発生し、ショッピングセンターの撤退による建物の放置が治安悪化の要因となっているケースもあります。
オーバーストアへの対策
オーバーストア化という大きな競争から生き残るには、どのような対策が必要でしょうか。最後に、オーバーストアへの対策として3つを解説します。
- 店舗の縮小
- 他店との差別化
- 経営資源の集中
店舗の縮小
冒頭にも解説したように、オーバーストアは、小売店舗などの商業施設が需要以上に出店していることで生じます。そのため、店舗の縮小を図ることで、店舗のある商圏内の需要を超えて供給が過剰になるという状況を防ぐことができます。
他店との差別化
店舗過剰の状況下で新たな需要を生み出すには、他店との差別化もポイントとなります。他店が真似することができないような商品・サービスを開発し、その商品・サービスへのこだわりや強みを違いとして明確化できることが重要です。ほかにも、ブランドや品揃え、顧客サービスといったことの他店との差別化もオーバーストア対策につながります。
経営資源の集中
オーバーストア化した商圏での競争に勝つために、あえて集中的に出店をする「ドミナント戦略」を図り、認知度を高めながら、競合の参入障壁も高めることで生き残りを図ります。そのためには、経営資源を一か所に集中させることが必要となり、さらに自店のみでその商圏の需要に応えられるようにすることが最終形であることから、競合が撤退するまでに耐えられる経営体力も重要となります。
まとめ

今回は、オーバーストアが生じる主な発生要因と、オーバーストアがもたらす悪影響とその対策について解説しました。オーバーストアとは、商圏の需要を超えて商業施設が出店している状態であり、積極的な出店や市場の変化によって発生します。ひとつの市場で需要を奪い合うことから売上の減少や最終的には撤退にもつながる問題です。店舗縮小や他店との差別化などで、オーバーストアの競争から抜け出せるような戦略が重要でしょう。
記事のURLとタイトルをコピーする